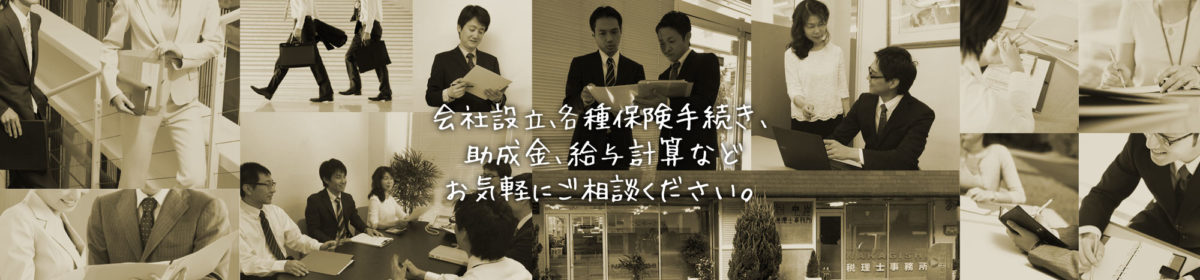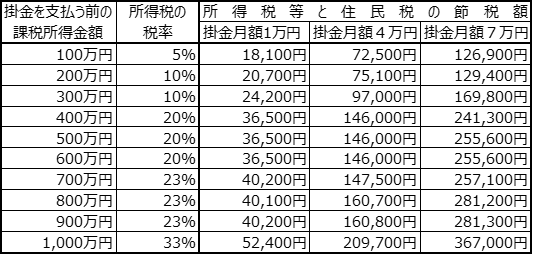○はじめてのブログ投稿です♪
みなさん、はじめまして。
中岸税理士事務所の不思議キャラJUNです。
とうとうブログデビューを果たす事となりました。
職場ではデリカシーのない発言が多くて引かれっぱなしですが、
ブログを炎上させないように気を付けてがんばります。
今回は消費税10%のお話です。
○10%になるとどうなる?
今年(平成?令和?)の10月1日から消費税が10%となります。
8%で買った方が得か、10%で買うと損になるのか、
いやいや、10%で買った方が差引く消費税が多くて得か?
といった話題が多くなってくるんでしょうね。
(ポイント還元は一旦無視です。)
結論から言いますと、
消費税の課税事業者にとって損得はありません!
消費税は、消費者(ほとんどの場合は一般個人)が負担して、
事業者(≒会社)が納付する税金です。
事業をされている経営者の方にとっては、
消費税の支払いに負担感を強く感じられるでしょう。
でも実際に負担しているのは、個人の方です。
会社は預かった消費税から支払った消費税を差引いて、
余った部分を税務署に納付しているだけなんです。
8%で仕入れた商品を、10%で販売しても、
10%で仕入れた商品を、10%で販売しても、
会社に残るお金(=利益)は全く同じです。
ただ、預かった消費税から支払った消費税を差引いて、
余った部分を税務署に納付しているだけなのです。
(だから気持ちよく払ってねって訳じゃないですよ。)
○具体的に考えてみましょう。
具体的に考えてみるとよくわかります。
税抜1,000円の商品を仕入れて税抜1,500円で売るとします。
【パターン① : 8%仕入・10%売上 】
仕 入 : 1,000円+消費税 80円
売 上 : 1,500円+消費税150円
利 益 : 1,500円-1,000円 = 500円
消費税額: 150円- 80円 = 70円(納付)
【パターン② : 10%仕入・10%売上 】
仕 入 : 1,000円+消費税100円
売 上 : 1,500円+消費税150円
利 益 : 1,500円-1,000円 = 500円
消費税額: 150円- 100円 = 50円(納付)
パターン①でもパターン②でも、利益が全く同じ500円です。
消費税の納付が70円か50円かの違いがあます。
でもパターン②では、仕入時に消費税を20円多く払っています。
この納付額の違いは、仕入先に支払うか税務署に支払うかの違いです。
つまり事業者側としては、仕入時期や販売時期で、
消費税の負担が変わったり、利益が変わったりはしません。
○誤解されている方が多いようです。
お分かりいただけましたでしょうか?
消費税を負担するのは、あくまで消費者です。
事業をしている会社が負担することは、ありません。
(※厳密に言えば様々な例外がありますが、省略です。)
ですから考えるべきは、負担の生じる消費者が、
8%で買うのか、10%で買うのか、ということですね。
ここに5%のポイント還元の話も出てきます。
キャッシュレス決済なら5%還元できますが、
キャッシュレス対応の設備投資や、
行政機関への登録が必要となります。
そこに様々な補助金制度が存在します。
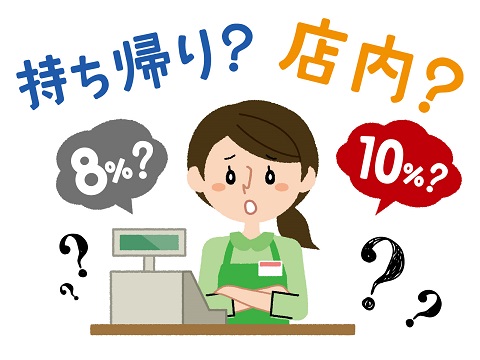
さらにさらに8%を据え置く軽減税率が!
消費税ってどんどん複雑になっていくなぁ。
個人的には増税延期の可能性が、
まだ残っていると思っているのですが、
みなさんはどう思われますか?